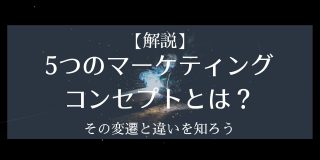マーケティング・ポジショニングで目指しているのは、顧客に「この商品は他とは違う」と認知し購入してもらうことです。そのために、自社商品のユニークなポジションを分析していきます。
自社のブランドのイメージを顧客に浸透させたい、競合とぶつかって成長曲線が鈍化した、このようなときに再定義したいマーケティング・ポジショニング。
本記事では、他社との関係の中で、自社の価値をどのように置けばいいのか、というポジショニングの方法論を、ポジションマップの作り方、成功事例を含めて網羅的にまとめています。
この記事のまとめ
マーケティング・ポジショニングとは、自社商品のユニークなポジションを確立して、そのイメージを顧客に認知させることです。
この分析には、ポジショニングマップ(パーセプションマップ)を活用します。これは、購買決定要因(KBF)を軸にした2軸のチャートを作り自社と競合との関係をマップ化したものです。
ビジネスのポジショニングは、一朝一夕で構築できるものではありません。マーケティング戦略全体で分析・調査を積み重ねて、ポジショニングを確立していく必要があります。
本記事では、ポジションマップの作り方からポイント、事例までひとつひとつ解説していきます。それでは、マーケティングにおけるポジショニングの定義からみていきましょう。
マーケティングのポジショニングとは?
マーケティングポジショニングとは、製品やサービスにおいて他社にはない独自のポジションを確立して、そのブランドイメージを顧客に浸透させることを指します。 例えば、
- 安くて早い食事を提供してくれるマクドナルド
- ステータスシンボルであるAudiやメルセデスベンツ
- ユーザフレンドリーな製品を提供するAppleやマイクロソフト
- 高級品質のコーヒーと非日常的な空間を提供するスターバックス
このような有名ブランドについては、名前を聞けば、誰でもどんな価値を提供してくれるのかが思い浮かびますよね。成功している会社は、ポジショニングが定義されブランディングを徹底しているため、顧客にどんな価値を提供しているのかを誰でも知っています。
マーケティング戦略では、定義した自社のポジションを実際にどうやって顧客に認知させるか、というところまでを含めて、「ポジショニング」としています。
顧客が他社の製品でなく自社のものを手に取ってもらうために、顧客の頭の中に自社のブランドや製品のイメージを確立するプロセスこそがこのマーケティングポジショニングです。
ポジショニングの重要性
上の例のように、よいポジショニング戦略をとることができれば、どんなに競争の激しい業界でも、シェアをとり安定した売れ行きや収益性を得られることが知られています。
アメリカの経営学者でマーケティング論の権威、フィリップ・コトラーは、1994年にSTP分析というマーケティング戦略の基本的なフレームワークを提唱しました。
このSTP分析は、「セグメンテーション(Segmentation)」「ターゲティング(Targeting)」「ポジショニング(Positioning)」の頭文字を示しており、現代のマーケティング戦略を考える際に、一番利用されている分析方法の一つです。
STP分析では、市場の細分化 (=「セグメンテーション」)、顧客の選定(=「ターゲティング」)を経て、狙っていく市場・顧客層を絞り込みます。この次に続くのが、ポジショニングで、どのような価値を提供して競合と差別化を図るのかを定義することになります。
その業界の中でのビジネスのポジショニングは、一朝一夕で構築できるものではありません。
このポジショニングで定義した、自社の提供価値やポジションは、そのまま次のステップである、4P分析や4C分析などのマーケティングミックスに使われ、最終的には、その製品設計や広告戦略、その他プロモーションなどに広く影響していきます。
マーケティング戦略全体を通して、細かい分析と地道なコミットメントを積み重ね、時間をかけてポジショニングを確立していくことになります。
ポジショニングマップ(パーセプションマップ)の作り方
ここでは、4ステップでポジショニングマップ(パーセプションマップ)を作る方法論を公開します。
ポジショニングマップとは、商品やサービスの提供価値を、縦軸と横軸に設定して、自社と競合他社を一目で比べられるような4象限のマトリクス図として表現したものです。
ポジショニングマップの完成度を高めることで、自社のポジションを明確に定義できるようになります。
STEP1:マップの軸となる購買決定要因(KBF)をブレスト
まず、ポジショニングマップの縦軸と横軸にするパラメータである購買決定要因(KBF)をブレインストーミングして、網羅的にあぶり出します。
購買決定要因(KBF)とは、「Key Buying Factor」の略で、顧客が商品・サービスの購買を決定する際に参考にする要因のことです。以下、具体例です。
- 金銭的軸 :安い、高い
- 機能的軸 :簡単、早い、複雑
- 感情的軸 :楽しい、爽快
- 精神的軸 :革新的、自由
- 外見的軸 :かっこいい、モダン、スタイリッシュ
- ステータス的軸 :権威性、希少性
顧客は、自社と他社の商品を見比べたときに、何の要素を決め手にして購入するでしょうか?これらを抜けもれなく列挙することで、商品・サービスのニーズをあらゆる角度から分析します。
STEP2:自社のターゲットがどのKBFを重視しているかを選定する
ここでは、ターゲットとする顧客が、先ほど列挙したKBFのうち、どの要素を重視しているのかを考えます。会社のひとりよがりなイメージで誤ったKBFを導かなようにするため、ターゲットの調査・分析が欠かせません。
顧客目線に立ち、実際に購買するときに検討するであろう要素を客観的なデータや調査に基づいて選定する必要があります。ここで選定したKBFが、「ポジショニングマップの縦軸と横軸」の候補になっていきます。
STEP3:選定したKBFを競合と比較する
そのKBFを評価対象として、自社と他社の商品・サービスを比較していきましょう。
例えば、「A社を1とするなら、B社は5」といったように相対的な点数でも構わないので、価値を点数化し、これを表にまとめると効果的です。この点数は、「ポジショニングマップ上の座標」になります。

STEP4:軸を決定し、4象限で表現してみる
実際にポジションをマッピングしてみます。軸を変えてマッピングするとマップの形相が大きく変わるはずです。どの軸を設定すれば、競合とポジションがかぶらないでしょうか。そのポジションが競合にもないユニークな価値だといえます。

ターゲットが重視している軸を優先して軸を決めるべきですが、もしよい軸の組み合わせがなければ、
- 見落としているKBF(軸)はないか
- ターゲットが競合と完全に重なっていないか
- そもそも自社の商品・サービスがありきたりになっていないか
このようなことを再度検討しましょう。場合によっては、マーケティング戦略を根本から見直す必要が出てくることもあります。
このマッピングによって自社の商品・サービスのポジションを、他社との比較の中で視覚的に表現することができます。このマップを洗練させることで、自社の商品・サービスに求められている価値を定義します。
ポジショニングマップ作成の注意点
「顧客視点」を持ち合わせること
「顧客は自社製品をこうやって考えるに違いない」、失敗するビジネスではこのような主観的な認識に強いバイアスがかかり、顧客の認識とのギャップが生じていることがほとんどです。
例えば、すこし前のモバイルPCでは、「CPU速度=大きな購買決定要因」でした。しかし、近年では、高価なPCを買わなくとも、十分に高速なCPUを搭載したPCが手に入るようになり、顧客は「CPU速度」よりも「バッテリーの持ち(消費電力)」を重視するユーザーが増えています。
- 顧客の実際の購買データ
- 市場や競合の分析
- 顧客のアンケート
などの定量・定性データに基づいて、顧客のニーズやウォンツを徹底的に分析し、購買行動の急速な変化に置いていかれないように、「顧客視点」をマップに反映させるようにしましょう。
ターゲットについて深く理解し、軸の「重み」を考える
ターゲットとする顧客が、自社と他社の商品のどちらを購入しようか迷っているときに最終的に何を基準に優れていると判断して購入するのでしょうか。こういったKBFの選定には、時間をかけて深く理解すべきです。
また、KBFの中には、例えば、その要素が少し変わるとターゲットの購買行動が大きく変わるなどの支配因子が含まれていることがあります。逆に、全く優先度の低いKBFもいくらでも挙げることができてしまいます。
そういった、軸の選択にも優先度があることを考慮に入れて、軸自体にも点数をつけて「重み」づけするようにしましょう。
相関の高い軸はマッピングに採用しないこと
よく、「価格」と「品質」を軸にとる人がいますが、「価格が高いと品質が高い」とった相関の関係を持った2軸でプロットすると、すべての商品・サービスが右肩上がりの直線上にのってしまいます。これでは、「価格」や「品質」を1軸にとったときと実質的にポジションは変わらず、2軸の意味がなくなってしまいます。
せっかく多次元の軸をとってポジショニングを定義するのですから、相関の高い軸は避けるようにしましょう。
常に変化し続ける市場環境では、定期的に検証することが重要
どのマーケティング戦略にもいえることですが、戦略は必要に応じて市場変化に適応できるように変えていかなければなりません。数年前の業界地図が数年後には過去のものになっている時代です。
自社のおかれている環境や、市場・消費者の変化、社会的な変化などがあれば、その都度、定期的に以下の項目を検証するようにしましょう。
- 競合と今でも差別化できているか
- ユーザーのニーズや価値観に変化はないか
- 顧客のニーズが本当にあるのか
- 市場ボリュームを把握できているか
- 市場の一般的なKBF(購買決定要因)は何か
- 自社製品をどのように認識してもらうか
ポジショニングを成功させるコツ
顧客視点と企業視点の両方を活用する
まったく他社にない技術を持っている、それは素晴らしい独自性です。しかし、「我々にしか作れない技術力」といった、企業側のユニークな価値だけを軸にとってしまうと、市場の共感性を失い顧客が離れていってしまいます。
常にこの2つは頭に入れて、企業視点だけではなく、必ず顧客視点が関わってくる軸も設定するようにしましょう。
企業理念やポリシーとポジショニングに整合性があるか
企業理念やポリシーは、言うなれば、企業自体のポジショニングです。企業と商品のポジショニングに矛盾があると、企業と商品両方のブランドに傷かついてしまいます。基本的には、企業理念やポリシーとポジショニングは、整合性を持たせるようにしましょう。
マーケティング・プロセスの一環として用いると効果的
先ほども少し触れましたが、ポジショニングはマーケティングプロセスの一環として用いられることが多いです。
マーケティング・プロセスとは、マーケティング戦略を立案してから実行するまでの一連の流れのことを指します。
主に、5つのプロセスに分けられます。

- マーケティングのマクロ環境分析(PEST分析)
- ミクロ環境分析(3C分析とSWOT分析)
- マーケティング基本戦略(STP分析:セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)
- マーケティングミックス(4P分析・4C分析)
- マーケティング戦略の実行・評価(戦略実行・評価⇄戦略の修正・再実行)
顧客や市場を定義しないと、ポジショニングは決まりません。そのため、まずはこのプロセスにしたがって市場・顧客の「分析」「絞り込み」をして、セグメンテーションや、ターゲットが定義できてからポジショニングを考えます。
また、ポジショニングは、次に続くマーケティングミックスと密接に関わってきます。マーケティングミックスは、企業が立案した戦略を、商品企画や広告、営業などの実際の行動にスムーズに落とし込むプロセスです。
マーケティング戦略全体を通して、細かい分析と地道なコミットメントを積み重ね、時間をかけてポジショニングを確立します。
マーケティングの戦略策定のプロセスに関する詳細な解説については、以下の記事をご覧ください。
ポジショニングの3つの事例を紹介
ポジショニングの事例を3つ紹介します。
コーラ戦争
コカコーラは、ご存知の通り最も歴史の長い飲料業界のリーディングカンパニーで、当時から世界的にブランドが浸透していました。
そこでペプシは、コカコーラの歴史と伝統を逆手に取って、若い世代にターゲットを絞ることにしました。マイケル・ジャクソンなどの超有名アーティストを広告に起用する戦略をとることで、「最先端」「革新的」「若さ」などのブランドを訴求したのです。
80年代から90年代にかけて、コカコーラとペプシの間で広告での宣伝が過熱しました。
その結果、ペプシの「若い世代向けの新しいコーラ」というポジショニング戦略が成功し、一時ペプシが市場シェア首位を獲得するという現象がおきました。コーラ戦争と呼ばれている有名な事例です。
ファストファッション
時代の影響を強く受けやすい、ファッションの業界ですが、それぞれの企業で印象がわかれ、細かく棲み分けがされています。
デザイン性では、ZARAとH&Mがトレンドによってデザインが決まっているトレンドファッションと呼ばれるポジションをとります。価格帯が異なり、H&Mの方が比較的ユーザー層が若い傾向にあります。
ユニクロは、安価で、トレンドに大きく依存しないベーシックなデザインです。シンプルで、多くのファッションとも合わせやすいと広く認知されているため、老若男女幅広い層から支持されています。
シーブリーズ
資生堂が展開するシーブリーズは、ポジショニングを大きく転換(リポジショニング)したことで売上を8倍に伸ばした商品ブランドです。
1902年にアメリカで誕生し、1970年代より日本でも資生堂が展開していたシーブリーズですが、20~30代の男性をターゲットに、「海」「夏」を意識させるブランディングを実施して1980年代に大ヒットを記録しました。
しかし、ブランドが高齢化するとともに、海にいく人が減り、日焼けを避けるというニーズが広まるに連れて、時代遅れのブランドとなって低迷したのです。
そこで資生堂は、ターゲットを10代に変えて、日常シーンでの使用を訴求することにしました。このように、築き上げたポジショニングを見直し、競合と別の戦略をとるリ・ポジショニングが功を奏し、現在まで学生に広く認知され大ヒットを収めています。